写真:記事作成者撮影(書籍『TSUYOSHI TANE Archaeology of the Future』/TOTO出版)
今回ご紹介するのは、田根剛建築設計事務所が、2018年TOTO出版により発売された、事務所初の作品集になります!私は建築学科で学び、設計の方法について悩んでいる時期にこの作品集に出会い、心動かされました。
今アイデアの出し方に悩んでいる方やデザインが面白くないと感じている方など。多くの方に、この本は新たな視点を与えてくれるはずです。
田根剛さんがどう考え、建築を作っているのか。
本を通して一緒に考え、見ていきましょう!
建築家 田根剛
まず、作品集をご紹介するにあたり、建築家田根剛さんについて見ていきましょう。
経歴
2006年:国際設計競技でエストニア国立博物館の設計を担当。10年をかけて2016年についに開館
2017年:「Atelier Tsuyoshi Tane Architects(ATTA)」を設立
思想について
田根さんは、紹介する本のタイトルにもある、「Archaeology of the Future」を大きな柱として考えられているそうです。直訳すると、「未来の考古学」。
「建築は、場所を記憶し、建築は未来の記憶となる。」
引用元:Archaeology of the Future 田根剛建築作品集 未来の記憶より
この、作品集にある言葉からも、単純にいい建築を作るだけではなく、設計した建築が未来への遺産として残ることを意識されていることが分かります。また、ふと自分や今の世の中について考えてみても、科学技術の発展とともに、新しいものがものすごいスピードで生まれています。しかし、そこに人の伝統や文化などがどれだけ残されているのだろうかと考えさせられました。
街を変えてしまうかもしれない、建築というスケールの大きなものを作る際において、この考えはとても重要なことなのかもしれません。
代表作品
代表作品として2つ紹介させていただきます。
1. エストニア国立博物館(2016年)
この博物館は、コロナ下を経て、10年という長い年月をかけ旧ソ連の軍用滑走路跡地に建設されました。エストニアの歴史と文化を象徴する建築として高く評価され、田根剛さんの名を世界に知らしめた作品といえます。
2. 弘前れんが倉庫美術館(2020年)
煉瓦倉庫を改修し、美術館として再生した建築。既存の煉瓦壁を保存しつつ、高度な耐震補強を施しました。このプロジェクトは、フランス国外建築賞(AFEX 2021)でグランプリを受賞しています。改修前の状態を残しつつも、今に残すものとして新たに再生させた田根剛さんを象徴するような建築です。
Archaeology of the Future 田根剛建築作品集 未来の記憶
それでは、作品集を紹介させていただきます。作品集には、完成している建築に加え、進行中の建築についても多く紹介されています。多くの写真などとともに本が構成されているため、パラパラとめくるだけでも楽しめます。しかし、この作品集について、ぜひ伝えたい私がお勧めするポイントが3つ!
①本の展開・構成の面白さ
②完成までの思考段階の多さ
③ワクワクさせてくれる言葉たち
①本の展開・構成の面白さ
1つ目のおすすめポイントが、「本の展開・構成の面白さ」です。
これまで作品集を20以上は手に取ってみたような気がします。そんな私個人の感想では、作品集でここまでプログラムの思考から形ができるまでを作品集を読みながら体験できたものはなかったように思います。
この作品集の流れは、次のようになっています。
(個々のコンテンツの説明は、私が読んで感じたものになります。)
①Manifest
建築家田根剛さんの建築に対する考えが書かれています。これを読むことにより、以降の内容がスッと入っていきました。
↓
②Concepts
1つ1つのプログラムが記載されていきます。ここでは、まずプログラムの基本的な情報(場所、歴史など)が書かれています。そこから、最終的な形になるまでの調査、スタディ、閃きの部分など。私が一番ワクワクした部分でもあります。なぜあの形になっているのか田根さんの考えとともに実感しました。
↓
③Images
本の構成として、図面よりも先に完成した建築や、イメージ模型などが写真として載せられています。
↓
④Drawings
ここで、ついに各建築の図面が載せられています。
↓
⑤Timeline
この作品集に紹介されている建築に加え、その他多くの建築物を設計されているか年代別に紹介されています。
①Manifestから始まるこの作品集は、しっかりと、どういった人の建築の作品集なのかを確認させてくれます。プロファイルとして、最後に載せられていて、あ、こういった人なんだな〜と後々知ることも多くないのが作品集だと感じていたので、他とは違うポイントですね!
そして、他の作品集と違う最大のポイントだと個人的に感じているのが、②Conceptsの存在です。
もちろん、他の作品集でも、作成者の考えは書かれながら進んでいきます。しかし、イメージ写真などと一緒に書かれていることが多いと感じていました。
構成の1つとして、分けられているこの順番により、①Manifestからスッとそれぞれの建築へと目線が移っていき、田根剛建築設計事務所としてどういった考えでそれぞれに向き合っているのか体験できました。
また、建築を学んでいるときに何度もつまずいた「どう考えて進めばいいんだ?いい建築ができるんだ?」について、1つの答えを示してもらった気がしました。この本に出会ってから、表紙が破れるまで読み、思考がクリアになり、思考がいい方向に進めたことを覚えています。
②完成までの思考段階の多さ
2つ目のポイントが、「完成までの思考段階の多さ」を実感できる点です。
主に②Conceptsについての内容かもしれません。田根剛さんは、1つの建築に対して膨大な量のリサーチをするそうです。そこから、どういったものが、未来への記憶として適切なものなのか判断されているのでしょう。
プログラムに対して、一部分ではありますが、重要なメモ、画像、スケッチ、模型などが紹介されています。ほとんど完成品に近いものもあれば、全く違うものも。そういった過程を経て一つの形ができているのだと感動します。
この思考段階を知ることは、きっと建築を学んでいる方、設計をされている方だけではなく、多くの方に影響を与えると思います。何も制作活動をされていない方でも、ふと街のイベント、建物など、起こっているものを考える時。その背景に何があるのか、どういった想いで作られたものなのか考えるきっかけになると思います。
③ワクワクさせてくれる言葉たち
最後に、「ワクワクさせてくれる言葉たち」というポイントがあります。
これは、作品集全体を通してそれぞれの部分に書かれている、田根剛さんの言葉になります。
例として、こちら!
「負の歴史を忘却するのではなく、抹消するでもなく、未来に繋げる。」
引用元:Archaeology of the Future 田根剛建築作品集 未来の記憶より
この言葉は、代表作品として紹介させていただいた、エストニア国立博物館についての説明として書かれていた一文です。
敷地が軍用滑走路であるため、実際には犬猿されることもあるであろうものを、新たな価値として生まれ変わらせつつ、未来へ伝える、繋げる大事な要素そして考えている部分だと思います。この建築に限らず、多くの建築に対して「未来に繋げる」を考えながら設計されており、実際にできた建築が多くの要素とともに、これから未来に繋がっていくのだな、未来ではどういった捉え方されるのかなと考えると、ワクワクせずにはいられません。
最後に
今回、建築田根剛さんによる、事務所初の作品集である「Archaeology of the Future 田根剛建築作品集 未来の記憶」を紹介させていただきました。
この本では、他の作品集ではなかなか感じることができないであろう思考から形が出来るまでを体感させてもらえます。あなた自身がそれぞれのプログラムと向き合い、私ならこういう形いいかもな〜、こういうのもありなのでは?と、自分なりの考えを出してみても面白いかもしれませんよ!
そういった考えは、きっとこれから生活する際、より生活のあらゆる活動を楽しくさせてくれる要素としてあり続けてくれるはずです!
ぜひ、みなさんもこの作品集を手に取って、読んでみてください!
<TSUYOSHI TANE Archaeology of the Future 田根剛建築作品集 未来の記憶>
著者:田根 剛
出版社:TOTO出版
発売日:2018年11月16日
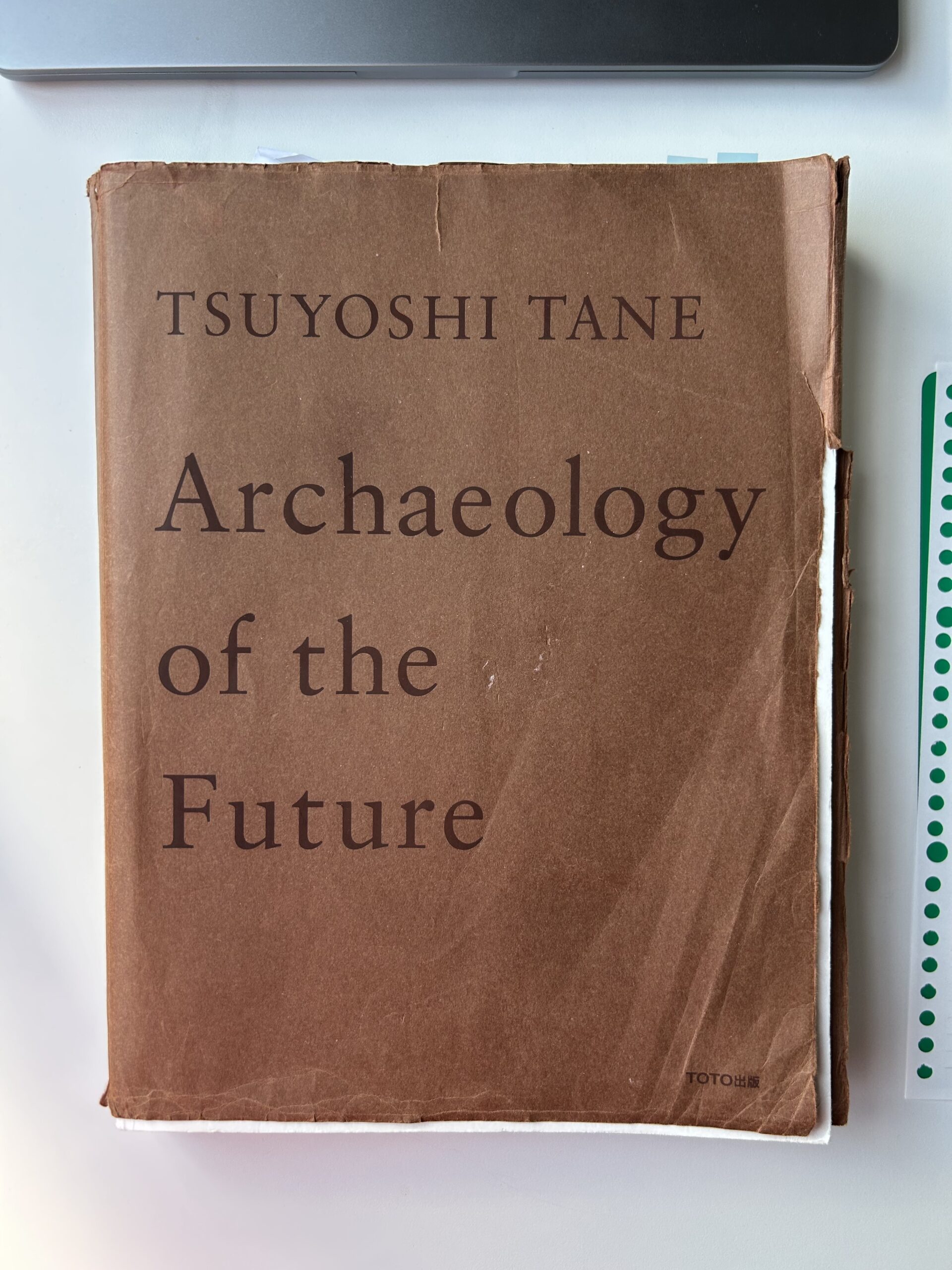

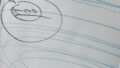
コメント